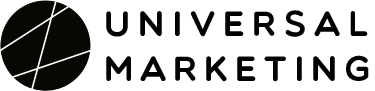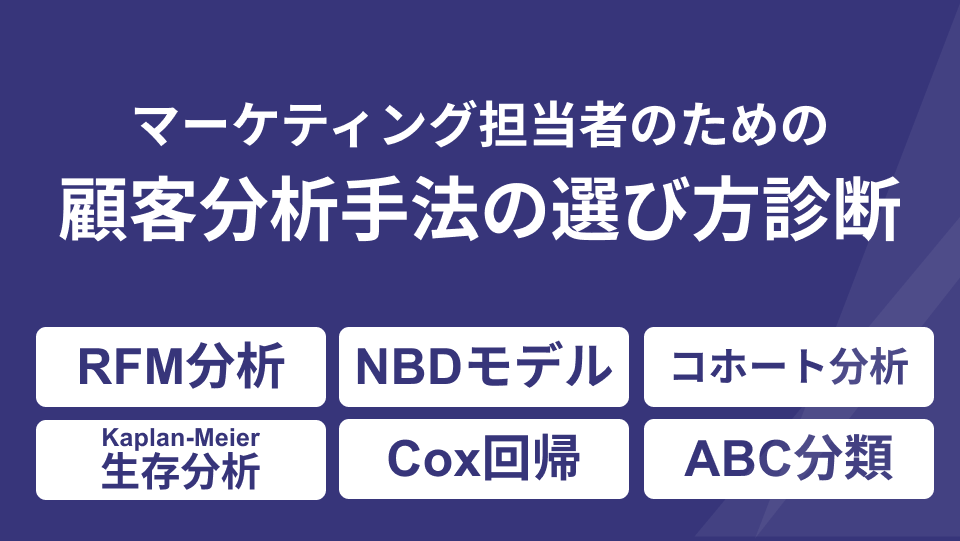事業への「適正投資額」を決める方法・シミュレーター付き
投資は「高い・安い」という感覚で決めるものではない。自社の稼ぐ力に対してどの規模なら失敗しても致命傷にならないか、どの規模なら当たれば跳ねるが外せば痛いか、どの規模なら会社が傾くか。この相対評価が投資判断の本質だ。わかりやすく三つのゾーンに切り分け、2年後の利益ROIで意思決定する。経営者は「いくらなら行けるか」を直感で測るのではなく、「いくらまで許容でき、当たるとどれだけ回収できるか」を規律で測るべきだ。
この記事の要点
- 投資判断は金額の大小ではなく自社利益との相対関係で決めるべきだ
- コンフォート/セーフティー/デンジャラスの三段階で整理できる
- ROIと失敗リスクを比較することで適正投資を見極められる
コンフォートゾーン:失っても揺るがない投資
コンフォートゾーンとは、失敗して投資額がゼロになっても会社の財務基盤に大きな影響を与えない領域だ。例えば、年商1億円、営業利益率50%で社員1名の会社なら、500万円の投資がこれに当たる。仮に全損しても経営は揺るがず、むしろリスクをとって成長の芽を探る健全な範囲と言える。
セーフティーゾーン:当たれば大きいが外すと痛い投資
セーフティーゾーンは、失敗すれば経営に痛手を与えるが、会社を傾かせるほどではない領域だ。例えば2000万円の投資で、当たれば年商が1億円増加しROI5倍が狙える事業である。失敗した際は痛いが、挑戦するに値する「攻めのゾーン」と言える。経営者の胆力が問われるのはこの領域だ。
デンジャラスゾーン:外せば会社が揺らぐ投資
デンジャラスゾーンは、失敗すれば会社の存続に影響しかねない投資領域だ。
例えば営業利益の50%に相当する5000万円を投資するケースである。ここでは判断を誤ると資金繰りや人員維持に直結し、経営が揺らぐ。成功すれば飛躍的な成長を実現できるが、経営者は慎重に資金調達手段や分散投資の戦略を持たなければならない。
ROIで投資判断を定量化せよ
投資を金額の多寡で決めるのではなく、自社利益に対する割合と想定ROIで整理すべきだ。2年後にRM(売上倍率)5倍が見込める事業なら、セーフティーゾーンに踏み込む価値は十分にある。
逆にROIが低い事業にデンジャラスゾーンの投資を行うのは経営判断として誤りだ。数字とゾーンの両面で投資を見極めることで、冷静な意思決定が可能になる。
ゾーン定義
- コンフォートゾーン:投資額 ≤ 「直近12か月EBITの10%」または「正味手元資金の10%」の小さい方。全損でも経営は揺らがない規模だ。
- セーフティーゾーン:投資額が「EBITの10〜40%」。外すと痛いが、資金繰りが破綻するほどではない規模だ。
- デンジャラスゾーン:投資額 ≥ 「EBITの40%」または「運転資金(3か月分固定費)の50%」。失敗すれば資金繰りと人員維持に直結する規模だ。
EBITの計算方法(簡易)
企業の税引前当期純利益から支払利息を足し戻し、受取利息があれば差し引くことで算出する。
税引前当期純利益 + 支払利息 – 受取利息
2年後の投資成功の是非を判断する計算式
会社の状況によって以下の3つの計算式を使い分けると良い。
売上倍率(RM)= 売上増加額 ÷ 投資額
利益ROI(2年)= 2年累計の営業利益増加 ÷ 投資額
必要成功確率(p*)= 1 ÷ (1 + 目標ROI(2年))
※例:目標ROI=1.5倍なら p*=0.40
※p*は「目標ROIから逆算される最小成功確率」だ。KPI(需要/獲得効率/継続性/供給余力/営業式)の4/5達成をp*充足とみなし、ROI(2年)が1.5倍以上なら「投資可」、1.0〜1.5倍は資金制約・戦略重要度で条件付き、1.0倍未満は「投資見送り」とする。
※用語定義:正味手元資金=現預金+当座預金−(1年以内返済予定の短期借入金)。運転資金(3か月分固定費)=人件費・家賃・サブスク等の月次固定費×3。TTM-EBIT=直近12か月の営業利益。
適正投資額シミュレーター
解説
活用シーン
企画の最初に「その額、会社としてそもそも踏めるのか」を10秒で判断したいとき。
稟議の“上限額”を先に決めて、検証に使う予算枠を素早く確定したい。
複数案件の配分(青=厚く、黄=段階投資、赤=見送り/資本政策先行)を決めたいときだ。
誰が使うか
経営者/CFO/事業責任者だ。まず資金制約のラインを引く人が使う。
出るものと使い方
青(コンフォート)=即検証でよい。
黄(セーフティー)=ゲート制前提で検証に進む。
赤(デンジャラス)=資本政策や分割案の設計が先だ。
注意
EBITは特異月を除いた直近12か月平均で見るべきだ。臨時損益はならすべきだ。
解説
活用シーン
施策の売上増加見込みと増分粗利率を置ける段階で、投資効率を定量比較したいとき。
A案・B案の相対優先(RMとROI)を決めたいときだ。
価格改定・媒体配分・チャネル新設などに向く。
誰が使うか
事業責任者/グロース担当/FP&Aだ。
配分の意思決定をする人が使う。
注意
RM(売上倍率)とROI(利益倍率)を混同しないことだ。本文の“5倍”はRMの話だ。
解説
活用シーン
不確実性が高く、成功確率pを主観で入れたくないときだ。
セーフティー/デンジャラス領域の大型投資を、段階停止込みで設計したいときだ。
稟議で「何をクリアしたら次の資金を出すのか」を明文化したいときだ。
誰が使うか
経営者/CFO/投資委員会/PMOだ。ゲート条件を定義する人が使う。
注意
デンジャラスでは5/5達成を原則にすべきだ。
KPI閾値は案件別に事前定義してから使うべきだ(例:LTV/CAC≥1.5、90日継続率≥35%…等)。
架空3社のケーススタディ
① 会社A:年商1億円・EBIT率50%・一人法人
- 現状:売上1億、EBIT5,000万、手元資金3,000万、固定費月300万と仮定だ。
- ゾーン閾値:
- コンフォート:≤ 500万(EBITの10%)
- セーフティー:500万超〜2,000万(EBITの40%=2,000万)
- デンジャラス:≥ 2,000万
投資案A-1(500万:新規広告×LPO改修)—コンフォート
- シナリオ:2年で売上+2,500万(RM=5倍)、増分粗利率40% → 2年利益増=1,000万
- 利益ROI=2.0倍(1,000万÷500万)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIは基準1.5倍を上回る(2.0倍)。実行だ。支出はゲート制(10%→30%→60%)で、KPIは4/5達成を条件に進めるべきだ。
投資案A-2(2,000万:新規プロダクト導入+販路開拓)—セーフティー
- シナリオ:2年売上+1億(RM=5倍)、増分粗利率28% → 2年利益増=2,800万
- 利益ROI=1.4倍、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIが基準1.5倍に未達(1.4倍)。見送りだ。まずはセーフティー内の有機的成長と改善でROI1.5倍を満たす筋を作ってから再審すべきだ。
投資案A-3(5,000万:大型M&Aの試し買い)—デンジャラス
- シナリオ:2年売上+2億、増分粗利率35% → 2年利益増=7,000万
- 利益ROI=1.4倍、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIが基準1.5倍に未達(1.4倍)。見送りだ。まずはセーフティー内の有機的成長と改善でROI1.5倍を満たす筋を作ってから再審すべきだ。
② 会社B:年商10億円・EBIT率15%・社員30名
- 現状:売上10億、EBIT1.5億、手元資金1億、固定費月6,000万と仮定だ。
- ゾーン閾値:
- コンフォート:≤ 1,500万
- セーフティー:1,500万超〜6,000万
- デンジャラス:≥ 6,000万
コンフォート例B-1(1,500万:自社ECのCX改善)
- シナリオ:2年売上+7,500万(RM=5倍)、増分粗利率35% → 2年利益増=2,625万
- 利益ROI=1.75倍(2,625万÷1,500万)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIは基準1.5倍を上回る(1.75倍)。実行だ。ファネル分解とA/B設計を並行し、ゲート制(10%→30%→60%)で進め、KPIは4/5達成を条件とすべきだ。
セーフティー上限付近例B-2(6,000万:新規D2Cライン+サブスクCRM)
- シナリオ:2年売上+3億(RM=5倍)、増分粗利率30% → 2年利益増=9,000万
- 利益ROI=1.5倍(9,000万÷6,000万)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIは基準ちょうど(1.5倍)。GoはKPI4/5達成を条件に、支出はゲート制(試作10%→テストローンチ30%→拡張60%)で実行し、未達ならそのゲートで停止すべきだ。
デンジャラス例B-3(1.2億:海外進出フルコミット)
- シナリオ:2年売上+5億、増分粗利率28% → 2年利益増=1.4億
- 利益ROI=1.17倍(1.4億÷1.2億)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIが基準1.5倍に未達(1.17倍)。見送りだ。まずは現市場でLTV最大化(解約低減・アド効率改善)等でROI1.5倍を満たす筋を作り、再審すべきだ。
③ 会社C:年商100億円・EBIT率8%・社員300名
- 現状:売上100億、EBIT8億、手元資金6億、固定費月4億と仮定だ。
- ゾーン閾値:
- コンフォート:≤ 8,000万
- セーフティー:8,000万超〜3.2億
- デンジャラス:≥ 3.2億
コンフォート例C-1(8,000万:データ基盤刷新+媒体最適化)
- シナリオ:2年売上+4億(RM=5倍)、増分粗利率25% → 2年利益増=1億
- 利益ROI=1.25倍(1億÷8,000万)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIが基準1.5倍に未達(1.25倍)。条件付きだ。ナレッジ資産化と恒常効率の改善が実測で示せることを前提に、KPIは3/5以上(望ましくは4/5)を条件とし、支出はゲート制(10%→30%→60%)で実行し、未達なら停止すべきだ。
セーフティー上限付近例C-2(3億:周辺カテゴリ参入)
- シナリオ:2年売上+15億(RM=5倍)、増分粗利率22% → 2年利益増=3.3億
- 利益ROI=1.1倍(3.3億÷3億)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIが基準1.5倍に未達(1.1倍)。見送りだ。撤退コストを低く設計(在庫回転・OEM条件・可変費化)し、既存販路の相乗などでROI1.5倍を満たせる筋が立った段階で再審すべきだ。
デンジャラス例C-3(5億:大型M&A)
- シナリオ:2年売上+25億、増分粗利率20% → 2年利益増=5億
- 利益ROI=1.0倍(5億÷5億)、p*(ROI目標1.5倍)=0.40|KPI判定:〔4/5=Go|3/5=条件付き|≤2/5=見送り〕|ゲート:10%→30%→60%
- 判断:ROIが基準1.5倍に未達(1.0倍)。見送りだ。PMIでの利益創出計画が具体化し、ROI1.5倍を満たす筋が立った段階で再審すべきだ。
実務での運用ルール(チェックリスト)
- まず比率で測る:投資額÷TTM-EBITでゾーンを確定するべきだ。
- 2年利益ROIで線を引く:1.5倍以上を基本合格、1.0〜1.5倍は資金制約・戦略重要度で条件付きだ。
- ゲート制分割:セーフティー以上は3段階に分割し、KPI未達で自動停止するべきだ。
- KPI下限で判定:プリローンチ・LTV/CAC・継続率・供給余力・営業式の4/5を達成=p*充足とみなす。
- キャッシュ防波堤:実行後も「固定費6か月分+運転資金」を死守するべきだ。
まとめ
- 投資は「500万円が高いか安いか」ではなく、「自社EBITに対する比率」と「2年後の利益ROI」で裁くのが正道。
- ゾーンで許容度を規定し、ゲート制とKPI基準でぶれない。
- 経営は確率のゲームだ。規律ある攻めが、会社を持続的に強くする。

本コンテンツはコンテンツ制作ポリシーにそって、当社が独自の基準に基づき制作しています。 >>コンテンツ制作ポリシー