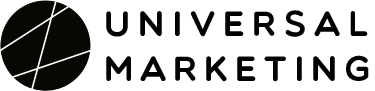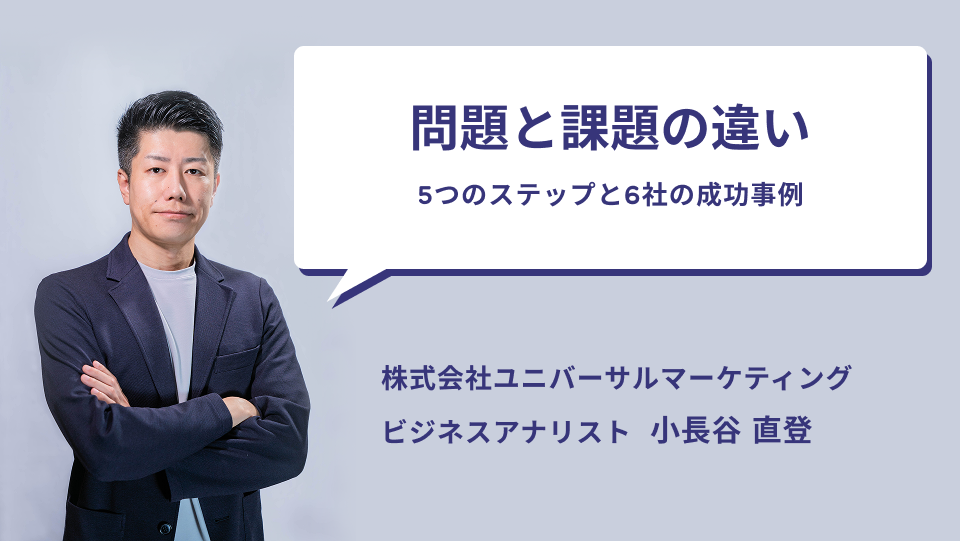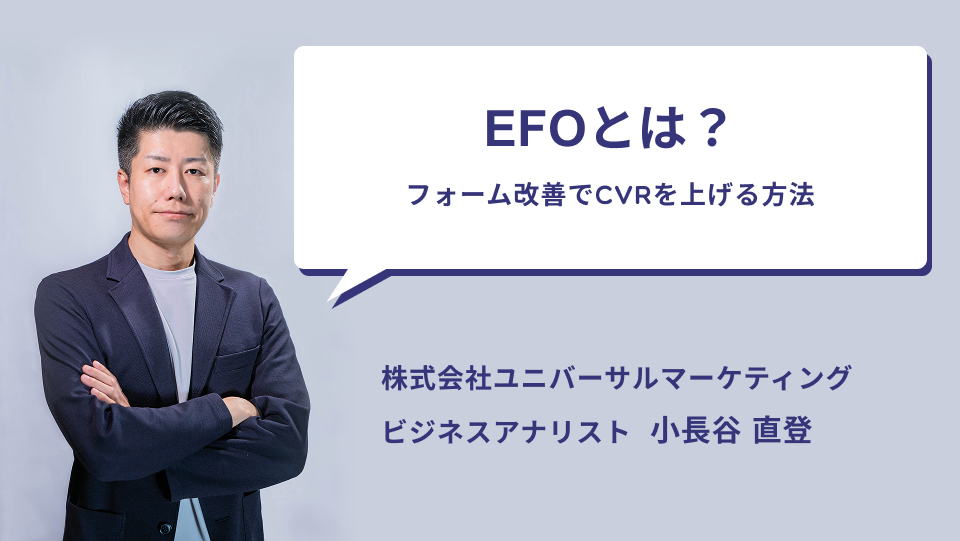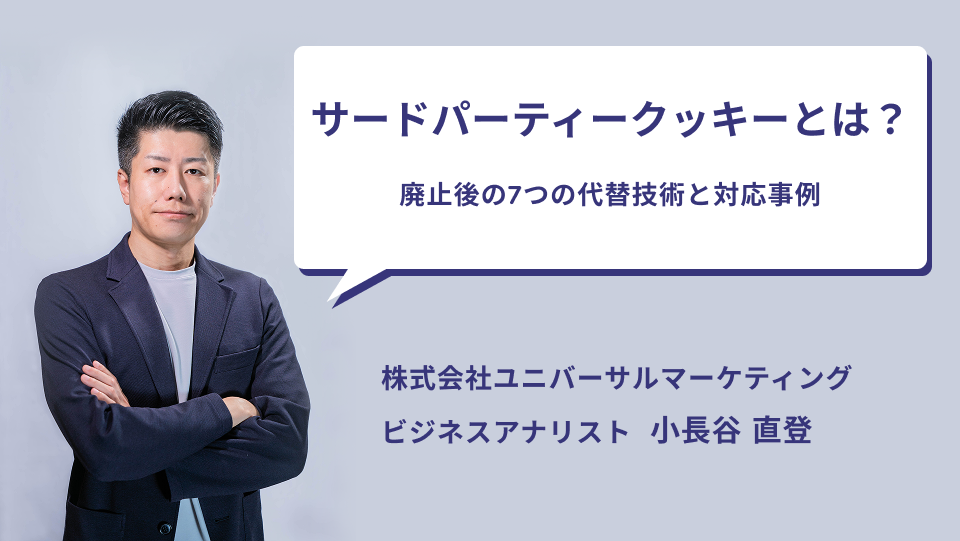
【2025年最新】サードパーティクッキー廃止後のマーケティング戦略|7つの代替技術と企業の対応事例
サードパーティークッキー(3rd Party Cookie)を巡る規制は急速に進み、マーケティング担当者や企業のウェブ担当者にとって避けて通れないテーマとなっています。本記事では、サードパーティークッキーの基礎から規制強化の背景、マーケティングへの影響、代替手段、成功事例、法規制の今後までを体系的に解説します。
この記事のポイント
- サードパーティークッキーの仕組みとファーストパーティークッキーとの違いを理解する
- GDPRや日本の改正個人情報保護法などの規制強化と各ブラウザの対応を把握する
- クッキーレス時代に向けた代替手段と成功事例を参考に自社施策を検討する
1.サードパーティークッキーとは?
クッキーとは、ウェブサイトを訪れたユーザーの情報を一時的に保存する仕組みであり、ユーザーが再訪問した際に同一のブラウザかどうか判別するために使われます。クッキーには発行元に応じてファーストパーティークッキー(閲覧中のドメインが発行)とサードパーティークッキー(第三者のドメインが発行)の2種類があり、前者はECサイトでのログイン状態や買い物かごの保持など利便性向上に用いられます。
一方、サードパーティークッキーは広告の効果測定やリターゲティング広告に活用され、別サイトにユーザーの行動履歴を伝えることで興味関心に合った広告表示を可能にしてきました。
ファーストパーティークッキーはユーザー体験の向上が目的であるため許諾が不要ですが、サードパーティークッキーはユーザー行動の監視につながるとして各国で規制が強化されつつあります。
2.規制強化の背景と最新動向
サードパーティークッキー規制の背景には、個人情報保護とプライバシー保護への高まりがあります。欧州連合では2018年にGDPR(EU一般データ保護規則)が施行され、個人データの利用に厳格な制限を設けました。日本でも2022年4月に改正個人情報保護法が施行され、クッキーを含む識別子の取り扱いが規制の対象となっています。このような流れを受けて、サードパーティークッキーを利用する際には原則としてユーザーの同意が必要とされるようになりました。
ブラウザ各社も独自に規制を強化しています。AppleはSafariにITP(Intelligent Tracking Prevention)を導入し、2020年3月のアップデートでサードパーティークッキーをデフォルトで全面的にブロックしました。
Googleは2020年にChromeでサードパーティークッキーを段階的に廃止すると発表しましたが、その後プライバシーサンドボックスの開発遅延や競争当局からの懸念を受け、2024年7月に廃止計画を撤回しユーザーに選択肢を提供する方針へと転換しています。
一方、企業や広告業界は代替技術の整備が追いつかず、廃止による広告収益の減少を懸念しています。
3.廃止による影響と課題
サードパーティークッキーが廃止されれば、リターゲティング広告やアトリビューション分析といったデジタル広告の基本的な仕組みに大きな影響が出ます。例えば、過去に訪問したユーザーに再度広告を表示するリターゲティング広告は、サードパーティークッキーがユーザー行動を認識することで実現していました。
廃止後はターゲティングの精度が低下し、CV率が悪化する恐れがあります。また、広告効果の測定も困難になり、ユーザーがどの広告を経由して購入に至ったかを把握するアトリビューション分析の精度が下がります。
さらに、サードパーティークッキーにはユーザーの名前や住所、クレジットカード情報など重要な個人情報が含まれる場合があり、不正アクセスによる情報流出への懸念も規制強化の要因となっています。
4.代替手段と対策
サードパーティークッキー規制に対応するためには、以下の代替手段が検討されています。
- ファーストパーティデータの活用:自社サイトで収集した顧客データや購買履歴をもとに分析・ターゲティングを行う方法。プライバシー保護を前提に、顧客管理システムやCRMを強化する必要があります。
- コンテキストターゲティング:ユーザーの行動履歴ではなく閲覧しているコンテンツの文脈に基づいて広告を表示する手法。個人を追跡せずに興味関心の近いユーザーに広告を届けられます。
- 共通IDソリューションやプライバシーサンドボックス:複数のドメイン間で同意を得た共通IDを利用したり、Googleが開発するプライバシーサンドボックスのAPIを活用することで、個人を特定せずに広告の効果を計測する技術です。
以下の比較表では、主な代替手段を項目別にまとめました。
| 項目 | ファーストパーティデータ活用 | コンテキストターゲティング | 共通IDソリューション |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 自社ドメイン内で取得した顧客データを分析し活用 | 閲覧ページの内容やキーワードに応じて広告を配信 | 同意を得たIDを複数ドメインで共有し広告配信 |
| メリット | ユーザー同意を得やすく、長期的な信頼関係を構築 | プライバシー侵害の懸念が少ない | リターゲティングや効果測定の精度を維持しやすい |
| デメリット | データ収集と管理の負担が大きい | 文脈だけでは広告効果が限定的な場合がある | 業界全体で標準化が進まず普及に時間がかかる |
| 適用場面 | 既存顧客へのアップセルやCRM施策 | コンテンツメディアやニュースサイトでの広告配信 | 大型広告主やプラットフォーム間連携が必要な場合 |
上記のように、各手法にはメリット・デメリットがあり、企業のビジネスモデルやターゲットに応じて組み合わせることが重要です。ファーストパーティデータ活用は顧客基盤の強化が前提となる一方、コンテキストターゲティングはプライバシーリスクが低く、配信先メディアの品質が成功の鍵となります。共通IDソリューションは今後の標準化や規制動向を注視しながら導入を検討すべき技術です。
5.成功事例とKPI分析
ここからは、クッキーレス時代に成功を収めている国内外の企業事例を紹介します。前章で触れた代替手段――ファーストパーティデータ活用・コンテキストターゲティング・共通IDソリューション――を実際に導入し、ビジネス成果を上げたケースをKPIとともにまとめました。各事例の公開日も明記しているので、情報の鮮度や再現性を確認しながらご覧ください。
国内事例(3件)
以下は日本企業の事例です。
| 事例タイトル | 企業名・業種 | 公開日 | 施策概要 (~100字) | 主要KPI(前→後) |
|---|---|---|---|---|
| Amplitude導入でファーストパーティデータ活用、ROI152%向上 | NTTドコモ/通信 | 2023-12-13 | 自社行動分析基盤を強化し、独自指標を発見。ユーザーLTV向上とROI改善を達成。 | ROI 100→252%、課金額/ユーザー6倍、分析工数 -96% |
| JREポイント会員データを活用したヒト起点マーケティング | JR東日本/交通 | 2023-06-01 | 1500万人の確定データに基づきJRE Adsを運用し、One to One広告を実現。 | CPA劇的改善(具体値は非公開)、レコメンドクリック率数%向上 |
| 価値に基づく入札でオフライン口座開設を最適化 | SBI証券/金融 | 2024-05-xx | オンライン広告データとオフライン口座開設データを統合し、最終KPIで最適化。 | 口座開設完了数 +13%、コンバージョン値 +22.9% |
他にもSMNの共通ID「IM‑UID」導入や、中小事業者のUGC活用事例などがあるが、定量指標や公開時期が限定的なため概要のみ補足に留める。
海外事例(2件)
次に、海外の先進事例を見てみましょう。
| 事例タイトル | 企業名・業種 | 公開日 | 施策概要 (~100字) | 主要KPI(前→後) |
|---|---|---|---|---|
| PAIR×ATSでコンバージョン率4倍を達成 | Omni Hotels & Resorts/ホスピタリティ | 2024-02-01 | Google PAIRとLiveRamp ATSを組み合わせ、同意ベースの認証IDで既知顧客に広告配信。 | コンバージョン率 1.0→4.0(4倍) |
| データクリーンルームで類似オーディエンスを構築しCTR129%増 | スイス大手銀行/金融 | 2024年2〜3月 | Decentriqのデータクリーンルームでファーストパーティデータを安全に統合し、プレミアム媒体で配信。 | CTR +129%、ページビュー単価 -44% |
事例と代替手段の対応関係
上記の事例は、各企業がどのような手法でクッキーレス環境に適応しているかを示しています。
・NTTドコモとJR東日本は、膨大な顧客データを分析するファーストパーティデータ活用によりROIやCPAを改善した例です。
・SBI証券の事例は、オンライン広告のKPIをオフラインの口座開設データと結び付けることで、最終事業成果に最適化する「データ統合」のアプローチです。
・Omni Hotels & Resortsでは、認証ID(PAIR×ATS)を用いて同意ベースの広告配信を行い、サードパーティークッキーに依存せずにコンバージョン率を4倍に向上させています。
・スイス大手銀行の事例は、データクリーンルームを活用して類似オーディエンスを生成し、プライバシーを確保しながらCTRを129%増加させたものです。
こうした対応関係を意識することで、前章で紹介した代替手段と実際の成果がどのように結びついているかが明確になり、自社での活用イメージが持ちやすくなります。
6.法規制と今後の展望
サードパーティークッキー規制は今後も世界各国で強化されると予想されます。日本では改正電気通信事業法が施行され、情報通信事業者に対して利用者情報の適切な取り扱いを義務付けています。米国でも州単位でプライバシー法が制定され、EUはePrivacy規則の制定を進めています。ブラウザベンダー各社は、ユーザーに対してクッキーの利用可否を明示的に選択させるUIを導入し、個人を特定しない形で広告の効果を測定する技術開発を続けています。
企業にとっては、規制の変化に適応するだけでなく、ユーザーの信頼を高めるデータガバナンスの体制を構築することが重要です。ファーストパーティデータを中心に据えたマーケティング戦略へ移行し、プライバシー保護と広告効果の両立を図る取り組みが求められます。
7.まとめ
- サードパーティークッキーは第三者ドメインが発行し広告測定に利用されてきた
- GDPRや日本の改正法を契機に規制が強化され、ブラウザ各社も対応を進めている
- 廃止によりリターゲティングや計測精度が低下するなど課題がある
- ファーストパーティデータ活用・コンテキストターゲティング・共通IDが主な代替手段
- 法規制の動向を注視しつつ、ユーザー信頼を高めるデータ活用が重要になる

本コンテンツはコンテンツ制作ポリシーにそって、当社が独自の基準に基づき制作しています。 >>コンテンツ制作ポリシー